

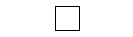
1、革にお酒を吹きかけるのは良くありません!
よくお祭りなどで景気づけにお酒を太鼓に吹きかける方や地方もあるようです。
お酒は、アルコールに揮発性があるため乾きが早く、水で濡れるよりはマシですが、
できることならお避けください。ましてや「太鼓に良い」ということは絶対にありません。
2、叩く場所を出来るだけまんべんなく散らばせて叩く。
革の一箇所を決め打ちしてそこばかり叩くと、その場所のみ磨耗して穴が空いてしまいます。
他の場所がいくらきれいでも、革に一箇所穴が開くと、良い音は出ません。
「張替え」ということになってしまいます。
私たちが革張替えのご依頼で張り替える太鼓の中にそういった太鼓がたまにあります。
どうしても叩き手さんのクセがありますので、
万遍無く革を叩き分けるのは意外と難しいのですが、
意識して試していただくことをお勧めいたします。
そうすることで革の耐用年数が変わってきますし、
まんべんなく革を叩く=革「全体」がやわらかくなる=音の響きが良くなるという効果もあります。
3、胴のふち(かど)や胴本体を叩かない。
これも地方や団体によって独特の叩き方があって難しいのですが、
よく胴のふちや場合によっては胴本体の真ん中を合いの手のように叩かれる方がいらっしゃいます。
出来ればこれも避けた方が良いでしょう。
あまり胴のふちを叩きすぎると、角が丸くなり、
それによって革の緩みが極端に早くなります。
また角が丸くなるだけならまだしも、
場合によっては胴のふちが内側に折れ込んでしまい、
大幅な修理を余儀なくされてしまいます。
胴本体真ん中を叩かれるのも、胴がへこみ傷ついてしまい、
こちらも場合よっては太鼓の耐用年数を縮めてしまいます。
合いの手に「カッカ」という硬い音が必要な演奏の場合、
胴のふち(かど)や胴の真ん中を叩かず、
革を留めてある鋲を叩くようにしていただくと良いと思います。
これであれば太鼓胴本体に破損をきたしません。
バチは確かにへこみやすくなりますが、
太鼓本体を修理することを考えると、はるかに経済的です。
また、どうしても太鼓胴本体や胴のふち(かど)を叩く必要がある場合は、
ヒノキなどやわらかい素材のバチをお勧めします。
またご修理・新規ご注文の場合に、胴を叩かれる旨おっしゃっていただけば、
ある程度事前の加工にて対応できますので、お取り扱い業者様にその旨ご相談ください。